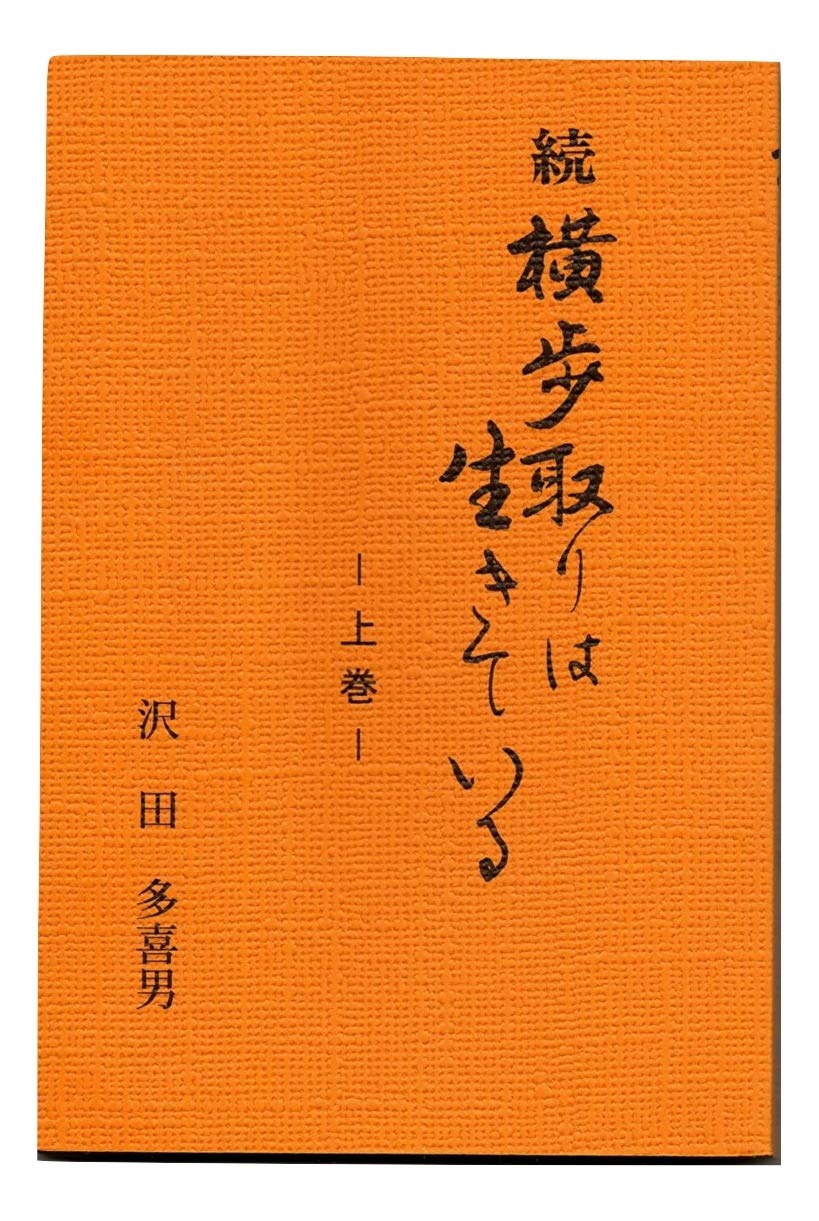本ページはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
スポンサーリンク
目次
◆【名局スクリーン】まぼろしの大野・大山十番将棋 角落ち戦を並べる
上記の記事の棋譜解説が一気に進み、盤面が追いにくい方がいると思いましたので、こちらで盤面図多く使って「まぼろしの大野・大山十番将棋 香落ち戦」を並べます。
上記の記事の棋譜解説が一気に進み、盤面が追いにくい方がいると思いましたので、こちらで盤面図多く使って「まぼろしの大野・大山十番将棋 角落ち戦」を並べてみました。
1940年9月8日、木見金治郎先生宅で開催された「第二十四回 木見会」で指されたまぼろしの一局です。
当時29歳の大野源一七段対17歳の大山康晴四段の新鋭同士の戦いが今ここに!
※この棋譜は将棋天国社から許可を頂いて掲載しています。
◇この一局の注目ハイライトシーン!「大山の受け」
まず今回、見て頂きたい注目の局面はこちら!
下図の次の一手を考えてください。
 【ハイライト図は△8二飛まで】
【ハイライト図は△8二飛まで】
上手が8筋を狙った局面。大山の受けが出る。
上手の大野先生が△8二飛として、次に△8六歩を狙った局面。
この局面、次の後手の8筋攻めを受けるのが難しいのです。
ハイライト図*で▲7五角*には△6四銀 ▲4八角 △8六歩*で8筋突破が受からない。
他にハイライト図*で▲8八飛*は△7六歩*~△6四銀*~△7五銀左*があって面倒。
ではハイライト図*で▲5九角*のような手では、△6四銀*~△6六歩*から6筋を狙われて下手大変。
既に下手の大山先生が困ったかのような局面ですが、ここで振り飛車陣の左辺を凌ぎ切って右辺を捌く「大山の受け」が登場します。
では見所を理解した所で「大野の攻め対大山の受け」がぶつかる、まぼろしの角落ちの一局を鑑賞していきましょう。
スポンサーリンク
◆まぼろしの大野・大山十番将棋 角落ち戦 を棋譜並べ
対局日:1940年9月8日
場所:第二四回 木見会 木見金治郎宅 での一局。
手割合:角落ち
上手:△大野 源一 七段
下手:▲大山 康晴 四段
 【角落ち初形図】
【角落ち初形図】
大野・大山の幻の一局が始まる。
△8四歩 ▲7六歩 △6二銀 ▲7八銀
△6四歩 ▲6六歩 △5四歩 ▲5六歩(第1図)≫
 【第1図は8手目▲5六歩まで】
【第1図は8手目▲5六歩まで】
互いに5筋を突き合い様子見の序盤戦。
ここから上手の大野先生が普通の角落ち上手と違った、面白い序盤構想を見せます。
第1図を再掲載します。
 【再掲載 第1図は8手目▲5六歩まで】
【再掲載 第1図は8手目▲5六歩まで】
上手の大野先生に趣向が出る。
△9四歩 ▲6七銀 △8五歩 ▲7七角
△7二金 ▲7五歩(第2図)≫
 【第2図は14手目▲7五歩まで】
【第2図は14手目▲7五歩まで】
下手に▲7五歩と取らせる大野流の趣向。
大野先生は△7四歩と突かず△7二金と上がり、あえて下手に▲7五歩(第2図)と位を取らせます。
大山先生曰く「一旦位を取らせてから反撃する作戦です。」
スポンサーリンク
第2図を再掲載します。
 【再掲載 第2図は14手目▲7五歩まで】
【再掲載 第2図は14手目▲7五歩まで】
ここから下手はどこに飛車を振るのが良い?
△5二金 ▲7六銀 △6三金左 ▲6八飛
△5三銀 ▲4八玉(第3図)≫
 【第3図は20手目▲4八玉まで】
【第3図は20手目▲4八玉まで】
普通は下手三間飛車だが、この場合は四間。
角落ち下手が振り飛車を狙うなら三間飛車が定跡ですが、今回は7筋の位を取って▲7六銀型なので、6五地点を争点にして動ける▲6八飛の四間飛車。
大山先生曰く「この形では当然です。」
第3図を再掲載します。
 【再掲載 第3図は20手目▲4八玉まで】
【再掲載 第3図は20手目▲4八玉まで】
上手の大野先生はどう玉を囲う?
△4四歩 ▲3八玉 △5二玉 ▲5八金左
△3二銀 ▲4六歩 △3四歩 ▲2八玉(第4図)≫
 【第4図は28手目▲2八玉まで】
【第4図は28手目▲2八玉まで】
お互い玉を囲う駒組み段階。
下手の大山先生は▲2八玉(第4図)と深く堅く固める方針。
対する上手の大野先生は△4四歩~△5二玉~△3二銀~△3四歩と中住まいのバランス型。
スポンサーリンク
第4図を再掲載します。
 【再掲載 第4図は28手目▲2八玉まで】
【再掲載 第4図は28手目▲2八玉まで】
大野先生は左銀と左桂を活用していく。
△4三銀 ▲3八銀 △3三桂 ▲3六歩(第5図)≫
 【第5図は32手目▲3六歩まで】
【第5図は32手目▲3六歩まで】
美濃に囲って準備万全。ここで上手が動く。
ここで7筋の位を取らせた大野先生が、位をめがけて仕掛けて来ます。
第5図を再掲載します。
 【再掲載 第5図は32手目▲3六歩まで】
【再掲載 第5図は32手目▲3六歩まで】
ここから上手はどう動いてくるのか?
△8三金 ▲6五歩 △同歩 ▲同銀
△6四歩 ▲7六銀 △4二玉 ▲4七金(第6図)≫
 【第6図は40手目▲4七金まで】
【第6図は40手目▲4七金まで】
6筋の歩を切り飛角が使える形に。
大野先生が△8三金~△7四歩と動いてくる直前に、▲6五歩と6筋の歩を切って飛角の道を通した大山先生。
大山先生曰く「6筋の歩を切って飛、角の道が通ったので、指せると思いました。」
第6図を再掲載します。
 【再掲載 第6図は40手目▲4七金まで】
【再掲載 第6図は40手目▲4七金まで】
下手陣は準備万端。上手はそこへ勝負を挑む。
△7四歩▲同歩 △同金右 ▲7五歩
△8四金▲3七桂 △7二飛(第7図)≫
 【第7図は47手目△7二飛まで】
【第7図は47手目△7二飛まで】
7筋を狙いに飛金が動く。どう受けるか?
上手の大野先生は△7四歩の7筋交換から△8四金~△7二飛(第7図)と7五地点に狙いをつけました。
これを下手の大山先生は凌ぐ事ができるのでしょうか?
スポンサーリンク
第7図を再掲載します。
 【再掲載 第7図は47手目△7二飛まで】
【再掲載 第7図は47手目△7二飛まで】
ここからどう上手の攻めを受ける?
▲6六角 △7四歩 ▲7八飛 △6五歩
▲4八角(第8図)≫
 【第8図は52手目▲4八角まで】
【第8図は52手目▲4八角まで】
攻められた筋に飛角を利かす。振り飛車的対応。
▲6六角~▲7八飛と「戦いの起こる筋に飛車を振る」振り飛車の基本的対応。
大山先生曰く「7筋の兵力は、上手が飛金二枚で合計三枚、下手も飛角銀と三枚なので悪くなる筈はないと思っていました。」
第8図を再掲載します。
 【再掲載 第8図は52手目▲4八角まで】
【再掲載 第8図は52手目▲4八角まで】
対する上手はここから7筋を制圧する方針。
△7五歩 ▲同銀 △同金 ▲同飛
△7四銀 ▲7八飛 △7五歩(第9図)≫
 【第9図は59手目△7五歩まで】
【第9図は59手目△7五歩まで】
上手は銀を使い△7五歩と押さえた。
上手の大野先生は▲7五同飛に△7四銀~△7五歩(第9図)と持ち駒の銀を使って7筋を制圧します。
大山先生曰く「7筋の位は取られましたが、銀を打たせてしまったので、指し易いとみていました。」
スポンサーリンク
第9図を再掲載します。
 【再掲載 第9図は59手目△7五歩まで】
【再掲載 第9図は59手目△7五歩まで】
7筋を押さえられた。下手はどう手を作る?
▲2六歩 △1四歩 ▲1六歩 △8二飛(ハイライト図)≫
 【ハイライト図は63手目△8二飛まで】
【ハイライト図は63手目△8二飛まで】
次に△8六歩を狙う。意外と受け辛い手。
さて△8二飛まで進んだこの局面が最初に紹介したハイライトシーンです。
ここで上手の△8二飛(ハイライト図)が7筋を薄くした思い切った手。 狙いは7筋を餌にした△8六歩からの8筋突破。
例えばハイライト図*で▲7五角*だと△6四銀 ▲4八角 で△8六歩*で8筋を突破されてしまいます。
では他にハイライト図*で▲8八飛*だと、大山先生曰く「それだと7六歩*から6四銀*、7五銀*があって面倒です。」
さぁ、一見上手の攻めを受ける事に困ったハイライトシーン。
ここで下手の大山先生に「大山の受け」が登場します。 その一手とは?
スポンサーリンク
ハイライト図を再掲載します。
 【再掲載 ハイライト図は63手目△8二飛まで】
【再掲載 ハイライト図は63手目△8二飛まで】
ここで「大山の受け」が登場する。
▲7七金!(第10図)≫
 【第10図は64手目▲7七金まで】
【第10図は64手目▲7七金まで】
▲7七金と虎の子の金を手放す受け!
▲7七金(第10図)がハイライトシーンから登場した大山流の手堅い受け。
この手の狙いは本譜を進めるとわかりますが、上手の左辺の攻め筋を消し、銀冠を作って右辺の攻めを間に合わせる狙い。
第10図を再掲載します。
 【再掲載 第10図は64手目▲7七金まで】
【再掲載 第10図は64手目▲7七金まで】
下手は金を手放したが、その後の構想がある。
△6四金 ▲2七銀 △5五歩(第11図)≫
 【第11図は67手目△5五歩まで】
【第11図は67手目△5五歩まで】
大野先生も何とか動こうとするが。
上手の大野先生も△6四金~△5五歩(第11図)と動いてきます。 何とか動かないと下手に銀冠を作られてしまいます。
スポンサーリンク
第11図を再掲載します。
 【再掲載 第11図は67手目△5五歩まで】
【再掲載 第11図は67手目△5五歩まで】
下手の銀冠が完成する前に戦いにしたい。
▲5八飛 △5四銀直 ▲5五歩 △同銀(第12図)≫
 【第12図は71手目△同銀まで】
【第12図は71手目△同銀まで】
上手は5筋の歩を交換する事ができた。
上手の大野先生は△5四銀直~△5五銀(第12図)と5筋の歩交換に成功。
ちなみに第12図*で▲6七歩*と打って、次に▲5六歩で銀を殺す筋がありそうですが。
大山先生曰く「6七歩の時、5四金*でうまくゆきません。」
第12図を再掲載します。
 【再掲載 第12図は71手目△同銀まで】
【再掲載 第12図は71手目△同銀まで】
下手はここから手堅く囲いを完成させる。
▲3八金 △5四金 ▲5六歩 △6四銀(第13図)≫
 【第13図は75手目△6四銀まで】
【第13図は75手目△6四銀まで】
5筋は▲5六歩と打って丁寧に受ける。
上手の大野先生の△5五歩の歩交換に▲5八飛~▲5五歩~▲5六歩と手堅く受け、その間に▲3八金と銀冠を完成させました。
銀冠を作った大山先生の狙いが次の一手で明かされます。
スポンサーリンク
第13図を再掲載します。
 【再掲載 第13図は75手目△6四銀まで】
【再掲載 第13図は75手目△6四銀まで】
銀冠に組んだ意味が、次の一手で明かされる。
▲2五歩 △5二玉 ▲2四歩 △同歩
▲2二歩(第14図)≫
 【第14図は80手目▲2二歩まで】
【第14図は80手目▲2二歩まで】
右辺から2筋を攻めるのが狙いだった。
▲2五歩~▲2四歩~▲2二歩(第14図)からのと金攻めが銀冠を作った大山先生の狙い。
この手を間に合わせるのが、▲7七金の「大山の受け」の狙いだったのでした。
第14図を再掲載します。
 【再掲載 第14図は80手目▲2二歩まで】
【再掲載 第14図は80手目▲2二歩まで】
2筋にと金を作り、上手を急かさせる。
△6三玉 ▲2一歩成 △1三香 ▲2三歩(第15図)≫
 【第15図は84手目▲2三歩まで】
【第15図は84手目▲2三歩まで】
単純ながら厳しすぎると金量産攻め。
△6三玉と2筋から遠ざかる大野先生に、容赦なく▲2一歩成~▲2三歩(第15図)のと金量産攻め。
ですが大野先生もこのままでは終わりません。 ここから桂を使った反撃を見せます。
第15図を再掲載します。
 【再掲載 第15図は84手目▲2三歩まで】
【再掲載 第15図は84手目▲2三歩まで】
2枚目のと金作り。上手は動くしかなくなる。
△8六歩 ▲同歩 △6六歩 ▲2二歩成
△2五桂(第16図)≫
 【第16図は89手目△2五桂まで】
【第16図は89手目△2五桂まで】
歩の突き捨て、伸ばしからの桂交換。
△8六歩~△6六歩~△2五桂(第16図)が大野先生の厳しい反撃。
大山先生曰く「上手の8六歩から6六歩が大野さんらしい巧いさばきで、まだまだ大変です。」
スポンサーリンク
第16図を再掲載します。
 【再掲載 第16図は89手目△2五桂まで】
【再掲載 第16図は89手目△2五桂まで】
上手は桂を入手し両取りを狙う。
▲2三と △5七歩 ▲同金 △3七桂成
▲同玉 △6五桂(第17図)≫
 【第17図は95手目△6五桂まで】
【第17図は95手目△6五桂まで】
金の両取りがかかった。巧みな手順。
△5七歩~△3七桂成~△6五桂(第17図)と桂馬のふんどしで金の両取りをかけました。
このあたりの手順は「日本一の捌きの大野」の異名を遺憾なく発揮している、華麗な桂捌きです。
スポンサーリンク
第17図を再掲載します。
 【再掲載 第17図は95手目△6五桂まで】
【再掲載 第17図は95手目△6五桂まで】
ここから大野先生の猛攻が始まる。
▲6六金右 △7七桂成 ▲同桂 △6五歩
▲6七金 △8六飛(第18図)≫
 【第18図は101手目△8六飛まで】
【第18図は101手目△8六飛まで】
8筋突破に成功。
△7七桂成と金を取り、△6五歩~△8六飛(第18図)と飛車を捌き8筋突破に成功しました。
大野先生の攻めの強さも発揮され、構図は完全に「大野の攻め対大山の受け」です。
手に汗握る展開になってきました。
第18図を再掲載します。
 【再掲載 第18図は101手目△8六飛まで】
【再掲載 第18図は101手目△8六飛まで】
ここから大野先生の怒涛の猛攻が来る。
▲5五桂 △同銀 ▲同歩 △2五桂
▲2八玉 △8九飛成(第19図)≫
 【第19図は107手目△8九飛成まで】
【第19図は107手目△8九飛成まで】
飛車を成り、次に△2九金の詰めろ。
下手の大山先生も▲5五桂から5筋から強く反撃。
しかし△2五桂~△8九飛成(第19図)が厳しい手で、次に△2九金*までの詰めろです。
ここから大山先生の盤石の受けでピンチを凌ぎ、負けない形にしてしまいます。
スポンサーリンク
第19図を再掲載します。
 【再掲載 第19図は107手目△8九飛成まで】
【再掲載 第19図は107手目△8九飛成まで】
詰めろだが、大山先生は冷静に受ける。
▲2九桂 △6四金 ▲2四と △7六歩
▲2五と(第20図)≫
 【第20図は112手目▲2五とまで】
【第20図は112手目▲2五とまで】
手順に銀冠の頭にと金を乗せ、盤石の玉形に。
▲2四と~▲2五と(第20図)が下手の右辺を勢力圏にする受けの好手。
大山先生曰く「2九桂で受かるので大丈夫です。 それに右翼一帯は私の勢力圏になったので、入玉含みもあり、負けはないと思います。」
第20図を再掲載します。
 【再掲載 第20図は112手目▲2五とまで】
【再掲載 第20図は112手目▲2五とまで】
ここから大野先生は諦めず大山陣に迫る。
△7七歩成 ▲同金 △6六桂 ▲5七飛
△5八金(第21図)≫
 【第21図は117手目△5八金まで】
【第21図は117手目△5八金まで】
飛金両取りをかける厳しい攻めが炸裂。
大野先生は桂馬を入手し、△6六桂~△5八金(第21図)の飛角両取りが炸裂!
気の抜けない展開で、ここからの大野先生の攻めは相当なものです。
第21図を再掲載します。
 【再掲載 第21図は117手目△5八金まで】
【再掲載 第21図は117手目△5八金まで】
大野先生の攻めが突き刺さったようだが?
▲4七飛 △4八金 ▲同飛 △5六歩(第22図)≫
 【第22図は121手目△5六歩まで】
【第22図は121手目△5六歩まで】
歩を垂らす軽手。次の歩成をどう受ける?
下手の大山先生は▲4七飛~▲4八同飛と冷静に受けます。
そこで大野先生は駒台の歩に手を伸ばし△5六歩(第22図)。
と金作りを狙った軽手で、どう受けるべきなのでしょうか?
スポンサーリンク
第22図を再掲載します。
 【再掲載 第22図は121手目△5六歩まで】
【再掲載 第22図は121手目△5六歩まで】
▲7六桂も見えるが、ここで大山流の一手が。
▲6七金(第23図)≫
 【第23図は122手目▲6七金まで】
【第23図は122手目▲6七金まで】
盤上の金を活用する好手。
ジッと▲6七金(第23図)が落ち着いた大山流の金寄りの好手。 自玉に盤上の金を寄せていくテクニックです。
ここでは▲7六桂*から攻める手もありそうですが、△5七歩成*~△5八桂成*と攻められる手がやはり気になります。
大山先生曰く「わざわざ、と金を許すこともありません。 難しくして勝つより、分かり易く勝った方がいいですから。」
第23図を再掲載します。
 【再掲載 第23図は122手目▲6七金まで】
【再掲載 第23図は122手目▲6七金まで】
だが大野流の猛攻がまだまだ続く。
△9九龍 ▲7六桂 △6九龍 ▲6八金
△8九龍(第24図)≫
 【第24図は127手目△8九龍まで】
【第24図は127手目△8九龍まで】
下手の金を6八に呼び寄せて・・・。
上手の大野先生は、ここから下手の大山陣に猛攻を仕掛けます。
その下準備として大野先生は△9九龍から香を入手し、△6九龍と下手の金を▲6八金と引かせます。
途中の大山先生の▲7六桂が痛打に見えますが、この桂打ちも大野先生の反撃の足掛かりにされるのです。
スポンサーリンク
第24図を再掲載します。
 【再掲載 第24図は127手目△8九龍まで】
【再掲載 第24図は127手目△8九龍まで】
▲6四桂とするが、桂を渡した後に反撃が。
▲6四桂 △同玉 ▲6七歩 △7六桂(第25図)≫
 【第25図は131手目△7六桂まで】
【第25図は131手目△7六桂まで】
▲6八金を消す二枚桂の攻め。
大山先生の▲6四桂に、大野先生は△同玉から桂を入手し△7六桂!(第25図)
この桂打ちの狙いは、邪魔な▲6八金を消して7筋から入玉をする事です。
またしても大野先生の逆襲の猛攻が始まりました。
第25図を再掲載します。
 【再掲載 第25図は131手目△7六桂まで】
【再掲載 第25図は131手目△7六桂まで】
ここから大野先生の入玉大作戦が始まる。
▲6六歩 △6八桂成 ▲7六桂 △7五玉(第26図)≫
 【第26図は135手目△7五玉まで】
【第26図は135手目△7五玉まで】
△6八成桂と桂頭玉で入玉が決まったか?
大山先生も▲6六歩~▲7六桂と上手玉に王手をかけますが、グッと前に△7五玉(第26図)と出てきました。
この△7五玉が「桂頭の玉、寄せにくし」の状態になっているのと△6八成桂の存在が上部開拓に大きく、いよいよ上手の入玉模様確定となってきた感じです。
例えば第26図*で▲6八飛*だと△7七金*と打たれて入玉が決まりそうです。
スポンサーリンク
第26図を再掲載します。
 【再掲載 第26図は135手目△7五玉まで】
【再掲載 第26図は135手目△7五玉まで】
上手玉はまだまだ踏み込んでくる。
▲7七金 △8六金(第27図)≫
 【第27図は137手目△8六金まで】
【第27図は137手目△8六金まで】
▲同金と取ると△同玉で入玉される。
大山先生もここで勝負に出ます。 ▲7七金から大野先生の上部突破を阻止します。
対する大野先生も△8六金(第27図)*と打ち、▲同金*なら△同玉*で入玉が確定します。
困ったようですが、実はここまで大野先生の玉を△7五玉まで呼び寄せた手順は大山先生の読み通りだったのです。
何故ならここから大山先生は大野先生の玉を一気に押し返して寄せてしまうからです。
ここで大山先生は上手の入玉を阻止し、押し返す力強い寄せを見せます。
次の3手を是非考えてみてください。
第27図を再掲載します。
 【再掲載 第27図は137手目△8六金まで】
【再掲載 第27図は137手目△8六金まで】
大山先生はたった3手で入玉阻止する。
▲6四銀 △8五玉 ▲8七歩!(第28図)≫
 【第28図は140手目▲8七歩まで】
【第28図は140手目▲8七歩まで】
好手。△同金なら▲9六金で詰み。
▲6四銀と玉を追い、▲8七歩!(第28図)と打つのが寄せの好手。 この▲8七歩で△8九龍の利きを止めて無効化してしまいました。 正に一石二鳥の歩打ちです。
第28図*で△8七同金*だと▲9六金*で詰み。
他に第28図*で△7七金*も▲8六金*までの詰みです。
この歩が好手で、いよいよこの将棋の終幕が近づいてきたようです。
スポンサーリンク
第28図を再掲載します。
 【再掲載 第28図は140手目▲8七歩まで】
【再掲載 第28図は140手目▲8七歩まで】
ここからどう決めるか?
△7六金 ▲9六金 △8四玉 ▲7六金(第29図)≫
 【第29図は144手目▲7六金まで】
【第29図は144手目▲7六金まで】
金の力で上手玉を強く押し返した。
△7六金と桂を取った手に▲9六金~▲7六金(第29図)と上手の上部の守りの要の金を取り除きました。
上手の大野先生の玉が△8四玉と押し返され入玉阻止に成功です。
 【再掲載 第29図は144手目▲7六金まで】
【再掲載 第29図は144手目▲7六金まで】
上手の大野先生に残された手は?
△9三玉 ▲8五金左 △同銀 ▲同金
△8二香(第30図)≫
 【第30図は149手目△8二香まで】
【第30図は149手目△8二香まで】
まだまだ粘りを見せる大野玉。
大野先生は次なる方針を立てます。 それが△9三玉と引いて粘る手です。
以下▲8五金左~▲同金に△8二香(第30図)と香を打ち、まだまだ粘りを見せます。
ここで寄せ間違うと大変な事になります。 大野先生の必死の粘りは果たして通るのでしょうか?
スポンサーリンク
第30図を再掲載します。
 【再掲載 第30図は149手目△8二香まで】
【再掲載 第30図は149手目△8二香まで】
この粘りに対し落ち着いて対応していく。
▲7四金 △9二角 ▲7五金打 △7二桂(第31図)≫
 【第31図は153手目△7二桂まで】
【第31図は153手目△7二桂まで】
角桂香を打ち、なりふり構わない受け。
自陣に角桂香の三枚を打ち、大野先生も必死の粘りを見せます。
この△7二桂(第31図)も執念を感じる受けですが、大山先生はここから俗手で簡単に寄せます。
ここから5手で大野先生の玉を詰まします。 その足掛かりとなるのが次の決め手です。
第31図を再掲載します。
 【再掲載 第31図は153手目△7二桂まで】
【再掲載 第31図は153手目△7二桂まで】
△7二桂に対し5手で詰ます俗手の決め手が。
▲7三銀打! △6四桂 ▲8四金上 △同香
▲同金(投了図)≫
 【投了図は158手目▲8四同金まで】
【投了図は158手目▲8四同金まで】
最後は俗手の連続で詰み。
▲7三銀打が上手の大野先生の玉にトドメを刺す俗手の決め手。
放置は▲7二銀不成で打った桂を取られるので、上手の大野先生としては△6四桂と取るよりありません。
以下▲8四金上 △同香 ▲8四同金(投了図)まで進んで詰みです。
まで158手で下手の大山先生の勝ちです。
スポンサーリンク
◆今回並べた「まぼろしの大野・大山十番将棋 角落ち戦」大山先生自身の解説記事
この将棋は『季刊夏 将棋天国VOL.14』昭和57年7月10日発行 P30「<特別企画>大山康晴十五世名人に聞く ──まぼろしの大野・大山十番将棋」で大山先生自身が当時の状況を振り返りながら、対談形式で解説しています。
この一局がどこでどうして指されたのか? 升田幸三先生との角落ちの話も少しですが、こぼれ話としてあります。
◆今回の記事の棋譜&棋譜再生
◇Youtubeで動画再生して鑑賞
この記事で解説した棋譜をYoutubeで動かして再生できます。
◇KIFファイルでダウンロードして鑑賞
さらに今回解説した記事を「kifファイル」でダウンロードできます。
▼kifファイルの再生方法▼ Androidの方は「Kifu for Android(無料版)」で再生する事ができます。 iPhoneの方は『kifu for iPone』で再生する事ができます。 |
◆関連記事
◇まぼろしの大野・大山十番将棋 香落戦 将棋天国社と大山先生の対談記事Part2
こちらの記事でこの角落戦の後に指された、大野先生対大山先生の香落戦の記事があります。
1982年に将棋天国社が大山先生に対談形式で角落ち戦の解説を聞いた、今では貴重な転載記事です。(許可を頂いて掲載しています。)
△まぼろしの大野・大山十番将棋 香落戦 名局スクリーン 棋譜並べPart2
上のPart2の棋譜を初手から最終手まで30枚以上の図面を使って棋譜並べした記事です。
上記の記事では盤面が追いにくいという意見があったので、下記の記事で少しづつ手を進めた記事を用意しました。
香落戦で発揮される、振り飛車党必見の「大野流の日本一の捌き」をご堪能ください。
▽関連商品
・季刊 将棋天国 夏 第14号
・横歩取りは生きている─大橋柳雪から現代まで─
・続横歩取りは生きている 上巻
・続横歩取りは生きている 下巻
#この記事のQRコード

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
スポンサーリンク