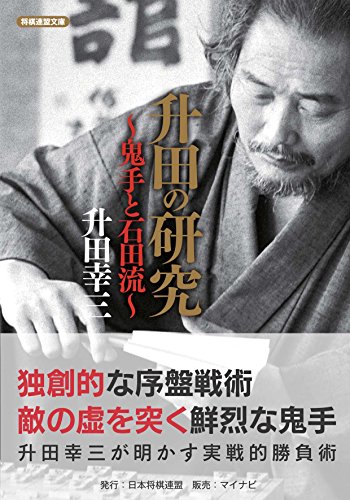本ページはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
スポンサーリンク
![]()
《「誰も知らないマイナー戦法」 全記事一覧へ移動する。》
【鏡の左早繰り銀 記事一覧へ移動する。】
<Part3の記事へ移動する。
Part1の記事へ移動する。>
目次
- ◆【第3回 誰も知らないマイナー戦法】 単純明快!「GAVA流 新鏡の左早繰り銀」Part2
- ◆「新鏡の左早繰り銀」ハイライトシーン
- ◆GAVA流「新鏡の左早繰り銀」8つのポイント まとめ
- ◆最後に「なぜ先手石田流へ有効なのか?」
- ◆GAVA流「新鏡の左早繰り銀」の対策:『金美濃▲8六飛戦法』
- ◆次回予告「升田流▲7七銀に挑む。無謀な強制相居飛車の角」
- ◆今回の記事の棋譜再生&kifファイルダウンロード
- ◆対石田流「鏡の左早繰り銀」&xaby角戦法 記事一覧
- ▽関連商品
- #この記事のQRコード
◆【第3回 誰も知らないマイナー戦法】 単純明快!「GAVA流 新鏡の左早繰り銀」Part2
◎前回の記事 ⇒ 【第3回 誰も知らないマイナー戦法】 早石田破りの必殺手!「鏡の左早繰り銀 新xaby角戦法」Part1 基礎編
◎鏡の左早繰り銀の記事一覧
●第3回 「鏡の左早繰り銀」・「xaby角」紹介記事一覧 ⇒ 第3回「鏡の左早繰り銀」記事一覧
◎『誰も知らないマイナー戦法』一覧【第1回~第3回】
●誰も知らないマイナー戦法一覧 ⇒「誰も知らないマイナー戦法」戦法集
前回のPart1(クリックでPart1の記事へ移動する。)で紹介した早石田破り「鏡の左早繰り銀」ですが、
先手に本戦法を封じる▲1六歩不突き(下記 参考A図)という対策がある事がわかりました。
 【参考A図は10手目▲5八金左まで】
【参考A図は10手目▲5八金左まで】
▲1六歩を突かない事が本戦法封じ。
1筋の突き合いを入れる事で、
後手は△5四角という必殺手を成立させたのですが
▲1六歩を突かない事でそれを封じられてしまいました。
では、本戦法は安定して使う事ができない不完全戦法…と思われたかもしれませんが
そんな事はありません。
本戦法には真の完成型が存在するのですから…!
(*の付いた青色の文字*を押すと解説が表示されます。)
「GAVA角戦法」*・「旧xaby角戦法」*の考案者のGAVA氏*が生み出した。
全ての変化に対応した「鏡の左早繰り銀」新型の駒組み方があるのです。
Part1で問題になった、
「先手に端歩を手抜きされると左早繰り銀へ組めない。」*
「序盤に▲4六角~▲7四歩と先手から動く手がある。」*
これら2つの問題点を解消し、
さらに「先手の囲いを美濃囲いへ限定させる。」
夢のような一手があるのです。
しかも序盤の手順を可能な限り簡略化し、
先手からの変化を全て消した、
早石田対策を手っ取り早く覚えたい将棋初心者の方でも会得しやすい戦法に昇華しました。
(なおPart1の長い講座は無駄ではなく、
本戦法を覚えた後の「序盤で得を狙うテクニック」へ繋がりますので、
このPart2の新型を体得した後に試す事をオススメします。)
スポンサーリンク
◆「新鏡の左早繰り銀」ハイライトシーン
今回のハイライトシーンを紹介します。
下のハイライト図をご覧ください。
 【ハイライト図は9手目▲5八金左まで】
【ハイライト図は9手目▲5八金左まで】
なんとここで石田流破りの角が登場。
先手角交換石田流の出だし。
後手の△4五角を消すため、▲5八金左(上記 ハイライト図)と上がった9手目の局面。
よくある角交換早石田の定跡形で、ここから△4二玉や△6二銀で通常の振り飛車対居飛車の将棋になるのが一般的な進行。
あるいはPart1のように、上記 ハイライト図から△1四歩~△2四歩~△2五歩~△2二飛と「鏡の左早繰り銀」を狙うのが考えられるでしょう。
しかし「鏡の左早繰り銀」を狙うなら、ここで△1四歩は実は確実性のない緩手。
よって上記 ハイライト図から
後手は持ち駒の角を使い「確実に左早繰り銀へ組む」新手を放ちます。
その一手とは…!?
スポンサーリンク
◇(初手から)先手の石田流宣言に△8八角成~「△2二銀!」
それではさっそく初手からの解説を始めましょう。
 【初形図】
【初形図】
新型「鏡の左早繰り銀」の紹介。
▲7六歩 △3四歩 ▲7五歩 △8八角成
(第1図)≫
↑≫の付いた青文字を押すと動く盤面で再生。
 【第1図は4手目△8八角成まで】
【第1図は4手目△8八角成まで】
まずは角交換。これに▲同飛だと?
(*の付いた青色の文字*を押すと解説が表示されます。)
先手の▲7六歩~▲7五歩に対し、後手は△8八角成といきなり角交換。
これは前回のPart1で解説した通り、先手の石田流本組み*を封じる狙いです。
この上記 第1図で先手には▲同銀・▲同飛の二つの変化があります。
まずは▲8八同飛の変化について語りましょう。
上記 第1図*では▲8八同飛*に、△1四歩* ▲1六歩 △4五角* ▲7六角* △2七角成 ▲4三角成 △3二金* ▲3四馬* △4二飛*と指したり、
他に上記 第1図*から▲8八同飛*に△4四角*と打つ、GAVA流オリジナル戦法がありますのでそちらの変化は下記の別ページで紹介させていただきます。
△(5手目 変化)GAVA流「新鏡の左早繰り銀」5手目で▲8八同飛なら?「二つのオリジナル戦法」
読みやすいよう、下記へ第1図を再掲載して手を進めます。
 【再掲載 第1図は4手目△8八角成まで】
【再掲載 第1図は4手目△8八角成まで】
ここから後手に工夫の一手が出る。
▲同銀 △2二銀!(第2図)≫
≫の付いた青文字を押すと↑動く盤面で再生。
 【第2図は6手目△2二銀まで】
【第2図は6手目△2二銀まで】
▲7四歩~▲5五角を封じた銀上がり。
なんと先手の▲8八同銀に「△2二銀!」といきなり銀を2二へ上がってしまいます。
Part1では、ここで△1四歩~△3二銀と凝った出だしでしたが
△2二銀!(上記 第2図)とする事で先手からの▲7四歩~▲5五角を絶対に生じないようにします。
(上記 第2図*で▲7四歩* △同歩 ▲5五角なら△9二飛*で先手の打った角が無駄になる。)
ただし先手へ△4五角と打つぞという幻影を見せ、
先手に▲6八飛の途中下車をさせる罠が消えるのがデメリットです。
・4手目△8八角成の角交換から△2二銀!これで▲7四歩~▲5五角を与えない。
スポンサーリンク
◇(6手目)▲7八飛に無骨に△3三銀!端歩を突かずに駒組みを進める。
読みやすいよう、下記へ第2図を再掲載して手を進めます。
 【再掲載 第2図は6手目△2二銀まで】
【再掲載 第2図は6手目△2二銀まで】
ここからも単調な手順を繰り出す後手。
▲7八飛 △3三銀 ▲5八金左
(ハイライト図)≫
↑≫の付いた青文字を押すと動く盤面で再生。
 【ハイライト図は9手目▲5八金左まで】
【ハイライト図は9手目▲5八金左まで】
△4五角を消す▲5八金左。なんとここで…。
後手は△3三銀と即上がる事で、先手からの▲4五角*のような筋違い角戦法の変化も与えません。
対する先手は▲5八金左と上がります。
もしここで▲4八玉*なら、以下△4五角* ▲7六角 △2七角成 ▲4三角成 △2二飛*と進み、互いに馬を作った力戦相振り飛車になります。
(以下▲6五馬 △7二金*と進み、駒損はないが先手は2筋の歩を取られているので玉を囲い辛い。後手は攻めに使いやすい4筋の歩が切れたので後手十分。)
スポンサーリンク
◇(9手目 ハイライトシーン)先手のあらゆる手を消した新手。速攻の△5四角!
下記にハイライト図を再掲載して、手を進めましょう。
この10手目で持ち駒の角を使った一石三鳥の新手が登場します。
 【再掲載 ハイライト図は9手目▲5八金左まで】
【再掲載 ハイライト図は9手目▲5八金左まで】
ここで盤上全体を睨む、名角が登場する。
△5四角!(第3図)≫
≫の付いた青文字を押すと↑動く盤面で再生。
 【第3図は10手目△5四角まで】
【第3図は10手目△5四角まで】
先手からの▲4六角を消した角打ち。
戻って本譜は▲5八金左に、いきなり△5四角!(上記 第3図)
この△5四角!の狙いは3つあります。
まず1つ目は、先手からの▲6五角を消す事。
2つ目は、この△5四角*に▲3八銀*と上がらせた後に即△2二飛*と振る事で、先手からの▲4六角*に△8二銀*と上がる受けを作る狙い。
そして3つ目は、先手を▲3八銀型の美濃囲いに強制させる事。
(もしこの上記 第3図*で▲2八銀*なら、以下△6二銀* ▲4八玉 △8四歩* ▲1六歩 △1四歩 ▲3八玉 △6四歩* ▲4六歩 △6三銀 ▲4七金* △8五歩*と居飛車にする。こうなると先手の▲2八銀型が壁形で後手十分。
さらに上記 第3図*で▲3八金*でも、以下△6二銀* ▲4八銀 △8四歩* ▲4九玉 △6四歩 ▲3九玉 △6三銀* ▲2八玉 △8五歩*と同様に指して、以下後手△4二玉*~△4四歩*~△3一玉*~△3二金*~△5二金*と囲えば、後に8筋の攻めが確実にある後手十分となります。)
相手からの▲6五角打ちの隙を消しつつ、
そのうえ▲4六角~▲7四歩も予防し、
先手の囲いを上部の攻めに弱い美濃囲いへ限定させた、
一石三鳥の角が、下記 再掲載 第3図の△5四角!なのでした。
 【再掲載 第3図は10手目△5四角まで】
【再掲載 第3図は10手目△5四角まで】
10手目の時点でも一石三鳥の名角。
ちなみに上記 再掲載 第3図*で▲7六角*は△同角 ▲同飛 △5四角* ▲2六飛に△2二飛*で飛車を振れて後手満足。
さらに上記 再掲載 第3図*で▲3六角*と打つのは、△同角 ▲同歩 △2二飛*(ここで▲6五角*だと、△6四角*で次の△1九角成から香を取る手が受からず後手有利。)と振り、次に▲2八銀* △5四角* ▲3七銀 △4四銀*から「鏡の左早繰り銀」の攻めが狙えて後手不満ありません。
(この▲3六角の変化は次の解説で出てくる大事な手順なので覚えておいてください。)
・1筋・2筋も伸ばさず△5四角!これで先手からの▲4六角~▲7四歩を予防!相手の囲いを美濃囲いへ限定!
スポンサーリンク
△(9手目 変化)△5四角と打つ前に△1四歩だと?
第3図で△5四角!と打つ手が新手とわかりましたが、
「この角を打つ前に△1四歩と突けないのか?」と思ったかもしれません。
本来なら△5四角と打つ一手前…。
9手目の▲5八金左*に△1四歩(下記 変化E1図)と突きたいのです。
 【変化E1図は10手目△1四歩まで】
【変化E1図は10手目△1四歩まで】
▲1六歩とさせて△5四角と打ちたい。
ここで先手が▲1六歩*と受けてくれれば、即△5四角*と打って、以下▲3八銀 △2二飛*以下本譜同様の「鏡の左早繰り銀」に組めて
本譜以上に1筋の端攻めがある後手が得をします。
しかし上記 変化E1図の△1四歩*に▲1六歩と受けず、▲4八玉!(下記 変化E2図)と指されると後手少々飛車を振りにくくなるのです。
 【変化E2図は11手目▲4八玉まで】
【変化E2図は11手目▲4八玉まで】
先手は少し飛車を振りにくくなる。
上記 変化E2図*で△5四角*と打ち
そこで▲3六角* △同角 ▲同歩の時に△2二飛*と振るのが先程解説した手順ですが
その時に先手から▲6五角!(下記 変化E結果図)で後手困ります。
 【変化E結果図は17手目▲6五角まで】
【変化E結果図は17手目▲6五角まで】
ここで△6四角と打てず、後手不満。
上記 変化E結果図で△6四角と打つのが先程解説した手順で出た受けですが…。
この場合だと上記 変化E結果図*から△6四角*に▲3七桂*と受けられてしまいます。
こうなってしまうと、後手は上記 変化E結果図から▲8三角成・▲4三角成に対して返し技もなく後手不満です。
無駄な変化をそぎ落とし、確実に組み切るのが
GAVA流「新鏡の左早繰り銀」なので
こんな変化が生じている時点で本戦法の思想に反しています。
本当は△1四歩・▲1六歩の交換を入れて△5四角と打ちたいのですが、
今回はあえて我慢して先に△5四角!(下記 再掲載 第3図)と打ったのでした。
 【再掲載 第3図は10手目△5四角まで】
【再掲載 第3図は10手目△5四角まで】
1筋を突きたいがあえて我慢。
もし序盤で少し得をしたい。
先手に端歩を受けずに指されても問題なく、別の指し方があるという方でしたら
△5四角と打つ前に、10手目で△1四歩と突く手をオススメします。
・本当は突きたいが、確実に飛車を振るために△1四歩も突かない。
スポンサーリンク
◇(12手目)△2二飛から姿を現す「左早繰り銀」…から、さらに単調な△4四銀!
下記へ第3図を再掲載して手を進めます。
 【再掲載 第3図は10手目△5四角まで】
【再掲載 第3図は10手目△5四角まで】
ここからも単純・単調。確実に組む。
▲3八銀 △2二飛(第4図)≫
≫の付いた青文字を押すと動く盤面↑で再生。
 【第4図は12手目△2二飛まで】
【第4図は12手目△2二飛まで】
いきなりの△2二飛!先手は既に忙しい。
速攻の△5四角を見て、先手は▲3八銀と上がるしかないのは先ほど解説した通り。
さて先手の▲3八銀に後手は△2二飛(上記 第4図)といきなり飛車を振ります。
この上記 第4図の△2二飛*に▲7四歩*なら、△同歩 ▲同飛に△4四銀*と出ておき、次に△7三歩と打てば先手は飛車の引き場所に困り後手不満ありません。(▲7六飛と引きたいのだが、△同角と取られるので引けない。)
△4四銀以下▲4八玉* △7三歩 ▲7五飛 △2四歩 ▲5六歩*に△6四歩* ▲5五歩 △6三角*と後手の角を追う展開が一例ですが、こうなると逆に先手の飛車が7五からいなくなった後に△5五銀と歩を取られる手があるので先手不満です。
さらにこの下記 再掲載 第4図は、
既に先手忙しい局面で、次の手が▲4八玉に限られています。
 【再掲載 第4図は12手目△2二飛まで】
【再掲載 第4図は12手目△2二飛まで】
先手の手は▲4八玉に限定されている。
例えば上記 再掲載 第4図*で先手が何もしなければ、次に△2四歩* ▲4八玉 △2五歩 ▲3九玉*に△2六歩* ▲同歩 △同飛*が2七地点を狙う厳しい攻めになり後手十分です。
では上記 再掲載 第4図*で▲4六歩*と突く手は、以下△2四歩!* ▲4七金 △2五歩!* ▲3六歩 △2六歩* ▲同歩 △同飛* ▲2七歩 △2二飛*と進み、次に△2八歩・△3五歩の攻めがある後手十分となります。
この手を防ぐためには、
先手最速で▲4八玉~▲3九玉~▲2八玉として
2八・2七地点の隙を消しにいかなければならないのです。
スポンサーリンク
局面を進めるので、
下へ第4図を再掲載します。
 【再掲載 第4図は12手目△2二飛まで】
【再掲載 第4図は12手目△2二飛まで】
先手は▲3八銀から美濃へ組むが…。
▲4八玉 △4四銀!(第5図)≫
≫の付いた青文字を押すと動く盤面で再生。↑
 【第5図は14手目△4四銀まで】
【第5図は14手目△4四銀まで】
この△4四銀で先手の▲3六角も消す。
よって本譜の先手は▲4八玉と上がりますが、
後手はいきなり△4四銀!(上記 第5図)と上がりました。
この手の意味は、上記 第5図の△4四銀*に▲3六角*なら△4五銀*とぶつける手を用意した物です。
せっかくなので先手からの▲3六角も消してしまうのが本戦法です。
とにかく単純に、単調に、確実に!
毎回同じ形に組み上げる事を目指しましょう。
・2筋を伸ばす前に△4四銀!これで先手からの▲3六角を消す。
スポンサーリンク
◇(14手目)2七地点を最速で狙う後手。ただし王手飛車に注意。
第5図を下へ再掲載して手を進めます。
ここから後手は、先手の美濃囲いの弱点を最速で狙いに行きます。
 【再掲載 第5図は14手目△4四銀まで】
【再掲載 第5図は14手目△4四銀まで】
美濃囲いの弱点の地点とは?
▲3九玉 △2四歩 ▲8六歩 △2五歩
(第6図)≫
↑≫の付いた青文字を押すと動く盤面で再生。
 【第6図は18手目△2五歩まで】
【第6図は18手目△2五歩まで】
2七地点を最速で狙いに行く…が。
飛車を振った後手は素早く△2四歩~△2五歩(上記 第6図)と2筋の歩を伸ばし、美濃囲いの弱点である2七地点を狙いにいきます。
ただし次にいきなり△2六歩から2筋の歩を切るのは悪手で、上記 第6図*から以下▲8五歩*に△2六歩*▲同歩 △同飛*と2筋の歩を切った瞬間に▲1五角*の王手飛車で後手敗勢となります。
△1四歩と突けていないデメリットですが、そこは「鏡の左早繰り銀」に組めた事に満足して目をつむりましょう。
・△1四歩と突いていないので▲1五角の王手飛車に注意。
スポンサーリンク
◇(18手目)王手飛車を消す△3三桂。…気がつくとそこは「鏡の国の左早繰り銀」の世界だった。
読みやすいよう、第6図を再掲載して局面を進めます。
後手は▲1五角の王手飛車を消すための手を指しますが、その手とは?
 【再掲載 第6図は18手目△2五歩まで】
【再掲載 第6図は18手目△2五歩まで】
▲1五角の王手飛車を消す手とは?
▲8五歩 △3三桂!(第7図)≫
≫の付いた青文字を押すと動く盤面で再生。↑
 【第7図は20手目△3三桂まで】
【第7図は20手目△3三桂まで】
王手飛車を消す△3三桂!
後手は王手飛車を消すため△3三桂!(上記 第7図)と跳ねました。
ここは△3三桂に代えて△1四歩*でも良いのですが、先手が▲1六歩と受けてくれないと一手パスのような手になるので
今回は速度を重視して△3三桂!(上記 第7図)と跳ねました。
これで上記 第7図*から次に△2六歩* ▲同歩 △同飛*の時に▲2七歩* △同角成*と上部から突破する手があります。
これで解説を打ち切っても良いのですが、
ここまで来たら美濃を崩し切るまでいきましょう。
再掲載 下記 第7図から手を進めます。
 【再掲載 第7図は20手目△3三桂まで】
【再掲載 第7図は20手目△3三桂まで】
次の△2六歩を受けるには?
▲2八玉 △3五銀!(第8図)≫
≫の付いた青文字を押すと動く盤面で再生。↑
 【第8図は22手目△3五銀まで】
【第8図は22手目△3五銀まで】
次の△2六歩で後手優勢!たった22手目。
後手の次の△2六歩を消すために、第7図から先手は▲2八玉と上がります。
それには△3五銀!(上記 第8図)と銀を五段目に上がりました。
こうなれば上記 第8図から△2六歩からの左早繰り銀の玉頭攻めがあり、特に今回は美濃囲いなので先手は玉頭攻めをモロに受ける格好になり後手優勢となります。
・組み上がったら△3三桂~△3五銀!「左早繰り銀炸裂!」
スポンサーリンク
◇(22手目)美濃の頭へ突き刺さる「絶対!左早繰り銀!」攻め合いを制する逆逃げの決め手
第8図から前回のPart1と同様に
先手▲7四歩と攻めて来ますが、
今回は先手美濃囲いなので後手の攻めが直撃します。
読みやすいよう、下記へ第8図を再掲載します。
 【再掲載 第8図は22手目△3五銀まで】
【再掲載 第8図は22手目△3五銀まで】
先手は既に潰れている。
▲7四歩 △2六歩! ▲同歩 △同銀
(第9図)≫
↑≫の付いた青文字を押すと動く盤面で再生。
 【第9図は26手目△同銀まで】
【第9図は26手目△同銀まで】
後手△2六歩~△同銀!まさに"必殺手"。
先手の2七地点は美濃囲いなので、もう既に受かりません。
なので第8図から▲7四歩と動く以外、指す手がないのです。
(第8図*で▲7六角*には△同角 ▲同飛 △5四角*~△2六歩。)
よって先手は第8図で▲7四歩と来ますが、後手は無視して△2六歩!と踏み込んできます。
(この△2六歩*に▲7三歩成は△2七歩成*で後手勝勢。)
よって▲同歩と取る一手ですが、△同銀(上記 第9図)となりました。
ここから後手の美濃囲いを必ず殺す一手が刺さります。
第9図を再掲載し、手を進めましょう。
 【再掲載 第9図は26手目△同銀まで】
【再掲載 第9図は26手目△同銀まで】
もう先手は逃れる術はない。
▲3九玉 △2八歩!(第10図)≫
≫の付いた青文字を押すと動く盤面で再生。↑
 【第10図は28手目△2八歩まで】
【第10図は28手目△2八歩まで】
先手玉を呼び寄せる鬼手。
第9図から、どうにもならない先手は▲3九玉と逃げます。
(ここで▲2七歩*は以下本譜と同じ手順になり、後手勝ちになる。)
この早逃げがなかなかの手で、後手の攻めが遠のいたかのように思いますが…。
そこへ△2八歩!(上記 第10図)
この手を見た瞬間、先手の背筋に冷たいものが走ります。
さてこの下記 再掲載 第10図、先手へ残された手はほとんどありません。
 【再掲載 第10図は28手目△2八歩まで】
【再掲載 第10図は28手目△2八歩まで】
ここで▲7三歩成の変化は?
この上記 第10図*で▲7三歩成*は、△2九歩成* ▲4八玉*(▲同銀*は△3七銀成*で後手勝勢。▲同玉*は△3七銀成* ▲3九玉 △2八飛成*まで。)に△2八と*から、次に△3八と* ▲同金 △2七銀成* ▲3九金 △6九銀* ▲6八飛 △3七成銀* ▲同玉 △5八銀成 ▲同飛* △3五桂*で後手勝勢となります。
長い手順ですが、先手玉へ後手の攻めが直撃しているので
王手をかけつつ迫るだけで、先手どんどん悪くなるのです。
スポンサーリンク
残るはもう一つ。
下記 再掲載 第10図の△2八歩に対し…。
 【再掲載 第10図は28手目△2八歩まで】
【再掲載 第10図は28手目△2八歩まで】
残るはここで▲5五角だが…。
上記 再掲載 第10図*で▲5五角*と打つ手には、
△4二玉!*(下記 変化F図)が7筋の攻めから遠のきつつ3三を守る手で後手優勢となります。
(下記 変化F図の△4二玉に代えて△4二金*・△3二金*も有力なのですが、この場合は劣ります。)
 【変化F図は30手目△4二玉まで】
【変化F図は30手目△4二玉まで】
7筋から玉を遠のく好手で後手優勢!
後手が序盤で頑なに△5一玉型を維持していた理由は、
この△4二玉の早逃げを用意するためだったのです。
ただし安易に序盤で△4二玉*と上がると、
その△4二玉型*を狙って▲3三角成* △同玉 ▲2五桂打*の攻めが生じたり。
飛交換後に▲2二飛(下記 参考B図)が痛打になるので、
飛車交換にならずに3三地点への攻めがなく、
先手が7三地点へと金を作りに来たタイミングで△4二玉と上がるのがコツです。
(それ以外の状況なら△4二金・△3二金を推奨。)
 【参考B図は51手目▲2二飛まで】
【参考B図は51手目▲2二飛まで】
この飛車打ちに弱くなる。
・先手の7筋攻めには7三から遠のく「△4二玉!」
スポンサーリンク
◇(28手目)もうどうにもならない…。「角で始まり角で終わる△8七金!」
では第10図を再掲載し、手順を進めましょう。
ここから諦めた先手が▲2八同玉と取る手を見て解説を終わりましょう。
 【再掲載 第10図は28手目△2八歩まで】
【再掲載 第10図は28手目△2八歩まで】
諦めた先手は▲同玉と取るが…。
▲同玉 △2七銀成!(第11図)≫
≫の付いた青文字を押すと動く盤面で再生。↑
 【第11図は30手目△2七銀成まで】
【第11図は30手目△2七銀成まで】
ここで▲同銀だと?
諦めた先手は第10図で▲2八同玉と取ります。
対する後手は待ってましたの…△2七銀成!(上記 第11図)
この上記 第11図の△2七銀成*に▲同銀*は△同角成* ▲3九玉 △4九馬* ▲同玉 △2九飛成* ▲3九銀 △3八銀* ▲5九玉 △3九龍* ▲6八玉 △8九龍*で、次に△6五桂~△6九金の必至を狙って後手勝ちとなります。
実戦だとこの手順で勝つことも多いので、上記の変化はしっかり覚えておきましょう。
スポンサーリンク
第11図を下へ再掲載し、手を進めます。
 【再掲載 第11図は30手目△2七銀成まで】
【再掲載 第11図は30手目△2七銀成まで】
先手は玉を逃げるしかない。
▲3九玉 △2八成銀! ▲4八玉 △3八成銀
▲同金 △2九飛成(結果図)≫
≫の付いた青文字を押すと動く盤面↑で再生。
 【結果図は36手目△2九飛成まで】
【結果図は36手目△2九飛成まで】
次に△2六桂・△6九銀があり後手勝勢。
さぁ第11図から先手は▲3九玉*(これに△3八成銀*は▲同金*で攻めが止まる。)と逃げた手に、
後手は△2八成銀!と入ります。
先手▲4八玉に、後手△3八成銀*(これに▲同玉*は△2七角成*~△4九馬*~△2九飛成*で後手勝勢。)と入り、
▲同金に△2九飛成(上記 結果図)と進み、桂得で飛車を成り込んだ後手勝勢となりました。
後手は上記 結果図*から、
次に△2六桂*~△3八桂成の詰めろと、
△6九銀*の割り打ちの銀もあり、
とても先手に勝ち目はありません。
なので先手は下記 再掲載 結果図から…。
 【再掲載 結果図は36手目△2九飛成まで】
【再掲載 結果図は36手目△2九飛成まで】
先手は▲3九金と引く事が多いが…。
先手は上記 再掲載 結果図*で
▲3九金*と引いて頑張るでしょうが、
以下△3六桂!* ▲同歩 △3七銀*が痛打で後手勝ちとなります。
そこから▲5九玉*に△3九龍 ▲4九銀 △8七金!* ▲6八飛 △3八銀成*(下記 参考C図)が一例で後手勝ち。
 【参考C図は46手目△3八銀成まで】
【参考C図は46手目△3八銀成まで】
途中の△8七金が決め手。
この手順の大事な所は△8七金!と打った手です。
そうなのです。
後手が10手目に打った△5四角は、2七地点を狙っただけではなかったのです。
「先手の美濃囲いを破壊した後に△8七金・△8七銀と打って左右挟撃を狙う。」
これこそ
GAVA氏が発見した新手
「10手で石田流を終わらせる一撃必殺の角」だったのでした…。
8七地点を△5四角と共に狙う手筋は、
本戦法では必ず出るフィニッシュブローなので
終盤で狙いましょう。
(他にも△7六桂*と打つ手もあり、終盤で△5四角は必ず生きます。)
・美濃を崩した後は△8七金(銀)!で左右挟撃。
ちょっとこれは上手く行きすぎた手順ですが、
序盤に先手が動いてくる変化を全て消して
毎回同じ形に組める「新型」に相応しい手順です。
まずはこのGAVA流「新鏡の早繰り銀」を覚え、
その後にPart1の手順を会得すれば
どんな状況でも本戦法を使う事ができるでしょう。
スポンサーリンク
◆GAVA流「新鏡の左早繰り銀」8つのポイント まとめ
最後に今回解説したGAVA流「新鏡の左早繰り銀」8つのポイントをまとめておきます。
1:4手目△8八角成の角交換から△2二銀!これで▲7四歩~▲5五角を与えない。(下図参照。)

【再掲載 第1図は6手目△2二銀まで】
これで▲7四歩~▲5五角を消す。
・ポイント1:『▲7四歩~▲5五角を消す△2二銀!』の解説へ移動。
2:1筋・2筋も伸ばさず△5四角!これで先手からの▲4六角~▲7四歩を予防!相手の囲いを美濃囲いへ限定!(下図参照。)

【再掲載 第3図は10手目△5四角まで】
即△5四角!▲4六角も打たせない。
・ポイント2:『▲4六角も消す、即△5四角!』の解説へ移動。
3:本当は突きたいが、確実に飛車を振るために△1四歩も突かない。(下図参照。)

【変化E1図は10手目△1四歩まで】
本当は突きたいが我慢。
後手としては△1四歩・▲1六歩の交換を入れてから△5四角と打てれば大満足なのですが、
実戦では上記の△1四歩に▲4八玉と上がられ、飛車を振れず困ってしまいます。
いっそ開き直って後手△1四歩*に▲4八玉*なら△1五歩*と伸ばし、 以下▲3八玉に△6二銀*から通常の居飛車にしてしまうという手もあります。
本戦法を指すならば、1筋の交換を入れる事だけは拘りましょう。
4:2筋を伸ばす前に△4四銀!これで先手からの▲3六角を消す。(下図参照。)

【再掲載 第5図は14手目△4四銀まで】
早期の△4四銀で▲3六角も潰す。
5:△1四歩と突いていないので▲1五角の王手飛車に注意。(下図参照。)

【上図は変化23手目▲1五角まで】
△1四歩がないため、この王手飛車に注意。
6:組み上がったら△3三桂~△3五銀!「左早繰り銀炸裂!」(下図参照。)

【再掲載 第8図は22手目△3五銀まで】
22手目!最速左早繰り銀炸裂!
7:先手の7筋攻めには7三から遠のく「△4二玉!」(下図参照。)

【再掲載 変化F図は30手目△4二玉まで】
先手の攻めから遠のく決め手。
8:美濃を崩した後は△8七金(銀)!で左右挟撃。(下図参照。)

【変化G図は44手目△8七金まで】
8七へ駒を打つまでが△5四角の仕事。
スポンサーリンク
◆最後に「なぜ先手石田流へ有効なのか?」
なぜこの△5四角が先手石田流に有効なのかを説明すると、
3手目に▲7五歩と突いて▲7八飛と振ってしまっているため
後手の△5四角が8七地点へ直通してしまっているからなのです。(下記 参考D図参照)
 【参考D図は10手目△5四角まで】
【参考D図は10手目△5四角まで】
▲7五歩型なので8七へ利きが直通。
もしもこれが▲7五歩と突いていない、
初手から▲7六歩 △3四歩 ▲6八飛とする
通常の角交換四間飛車相手に狙うと
下記の参考E図のようになります。
 【参考E図は10手目△5四角まで】
【参考E図は10手目△5四角まで】
7六に歩があるので先手やれる。
これも相当有力で
上図以下▲3八銀に△2二飛で後手かなりやれるのですが
△5四角を▲7六歩で止められているため
2七地点は突破できるものの、その後に8七地点を狙う事まではできないのでした…。
これぞGAVA氏考案の
10手で早石田を終わらせる
「鏡の左早繰り銀戦法」の極意なのでした…。
しかも本戦法には
Part2の確実に組む方法だけでなく
Part1で紹介した「序盤に大量の罠を仕掛ける定跡」もあり
石田流党にとっては悪魔のような戦法なのでした…。
では最後に本戦法へのちょっとした対策を一つ紹介して終わりましょう。
それが9手目▲5八金左に代えて、▲3八金と上がる手です。
スポンサーリンク
◆GAVA流「新鏡の左早繰り銀」の対策:『金美濃▲8六飛戦法』
決定的対策ではないのですが、
相手が「鏡の左早繰り銀」で来るとわかっているなら、
一発ネタですが、それを封じる作戦があるのです。
それが9手目で▲3八金(下記 変化H1図)と上がる手。

【変化H1図は9手目▲3八金まで】
この金上がりがちょっとした対策。
上記 変化H1図から
△5四角 ▲7六角(下記 変化H2図)と進み。

【変化H2図は11手目▲7六角まで】
ここで▲7六角が趣向の一手。
上記 変化H2図の▲7六角*に
△2二飛*は▲5四角 △同歩*で飛車は振れたものの
後の△5四角がなくなった後手少し不満。
なので上記 変化H2図から
△同角 ▲同飛(下記 変化H3図)と進みます。

【変化H3図は13手目▲同飛まで】
先手は飛車を浮いたが…意味は?
この上記 変化H3図で△2二飛は
以下▲6五角 △5四角 ▲同角 △同歩で
やはり後手△5四歩を突いて少し不満。
よって上記 変化H3図で△5四角と打ちますが、
先手▲8六飛!(下記 変化H結果図)と進み…!

【変化H結果図は15手目▲8六飛まで】
後手は飛車を振れなくなった。
この▲8六飛!が後手の飛車を振らせない珍妙手。
ここから後手は△2二飛だと▲8三飛成があるため、もう飛車を振れません。
よって上記 変化H結果図から△8四歩と進み
先手一手損ですが、早石田金美濃囲いの将棋となり一局。
慣れた石田流の将棋なら、先手も力を出し切れるでしょう。
無理に飛車を振らせないxaby角戦法から生まれた本戦法には
こちらも飛車を振らせない強引な一手!
これこそが
本戦法の最期に相応しい因果応報の対策なのでした…。
(ただし9手目▲3八金に△5四角と打たなければ、
金美濃囲い対居飛車の別の将棋となり互角だが後手も指せる。
決定的対策でないのは、そのため。)
スポンサーリンク
◆次回予告「升田流▲7七銀に挑む。無謀な強制相居飛車の角」
このPart2を読んだあなたはこう思ったかもしれません。
「1970年に升田幸三 実力制第四代名人が編み出した『升田式石田流』は終わってしまった…。」と。
しかしご安心ください。
実はこの後手4手目角交換には、本家升田流の対策があるのです。
 【次回予告図は7手目▲7七銀まで】
【次回予告図は7手目▲7七銀まで】
本家の全てを知り尽くした一手。
上の次回予告図がその一手で、
7手目で▲7八飛と振らずに
▲7七銀と指す手が、升田幸三 実力制第四代名人が
4手目角交換を挑まれた際に必ず指していた手。
(『升田の研究~鬼手と石田流~』《著:升田幸三》《クリックで商品紹介欄へ移動する。》でも解説されています。)
狙いは上記 次回予告図から▲8八飛として、ダイレクト向かい飛車にする事。
この升田流の一手へ
「鏡の左早繰り銀」の考案者のGAVA氏は無謀にも一つの対策を試みたのですが…。
ここから完全互角の相居飛車*へ持ち込む
純粋振り飛車党だけが青ざめる一手とは!?
旧xaby角から
新xaby角へ引き継がれた
「強制相居飛車」の角打ち!
お楽しみに!
◇次回の記事(Part3)
スポンサーリンク
◆今回の記事の棋譜再生&kifファイルダウンロード
この記事で解説した棋譜を動かして再生できます。

マイナー将棋ブログ 作『【第3回 誰も知らないマイナー戦法】 GAVA流「単純明快!新鏡の左早繰り銀戦法」Part2.kif』はクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
https://minorshogi.com/3st-minor-tactics-that-no-one-knows-part2/にある作品に基づいている。
▼kifファイルの再生方法▼ Androidの方は「Kifu for Android(無料版)」で再生する事ができます。 iPhoneの方は『kifu for iPone』で再生する事ができます。 |
◆対石田流「鏡の左早繰り銀」&xaby角戦法 記事一覧
▽関連商品
・早石田封じ xaby角戦法! 【定価:275円】
・振り飛車最前線 石田流VS△1四歩型 (マイナビ将棋BOOKS) 【定価:1,694円】
・升田の研究~鬼手と石田流~ (将棋連盟文庫) 【定価:1,353円】
#この記事のQRコード

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
スポンサーリンク